1. 『ずるい考え方』とは?
『ずるい考え方 硬い頭が柔らかくなる発想トレーニング』は、作家の木村 尚義さんが書かれた一冊の本です。この本は、日常的に使われる「ずるい」という言葉を、ネガティブな意味合いとは異なる新たな視点で捉えることから始まります。通常、「ずるい」とは、ルールを逸脱するずる賢い行為を指しますが、木村さんはこれを発想力を鍛える一つの方法として紹介しています。
この考え方を支えるのがラテラルシンキング(水平思考)です。ラテラルシンキングとは、固定観念にとらわれずに物事を多角的に見る思考法であり、ロジカルシンキング(論理的思考)とは対極に位置づけられます。例えば、飲み会で支払いを自分のカードで立て替え、その後ポイントを得るという行動は、表面的にはずるいと見られがちですが、れっきとした工夫であり、立派なラテラルシンキングの一例です。このような柔軟な発想が、時に周囲を驚かせることがありますが、それこそが「ずるい考え方」の醍醐味とも言えるでしょう。
さらに『ずるい考え方』では、ラテラルシンキングを磨くために必要な3つの力についても触れられています。まず第一に、「疑う力」です。これは常識を疑い、新しい視点を得るためのもので、日常的な事象に対しても既存のフレームワークを壊し、新たな可能性を探る力です。次に「抽象化する力」が挙げられます。これは、物事の本質を見抜く力であり、複雑な情報をシンプルにして、新しいアイデアを生み出す手立てとなります。そして最後に、「セレンディピティ(思いがけない発見)」の力です。この力は、偶然の出来事を最大限に活かし、予期せぬ価値を引き出す感性を養うことを目的としています。
これらの力を身につけることで、あなたも新しい視点や発想を簡単に手に入れられるでしょう。そして『ずるい考え方』を実践することは、ビジネスや普段の生活の中で、今まで見過ごしていた可能性に気づき、活用するきっかけとなるはずです。
2. ずるい考え方の具体例
飲み会での支払い方法を考えてみましょう。通常、飲み会での支払いは誰もが均等に負担することが一般的です。しかし、ルールを超えた柔軟な発想を用いると、支払いを一度自分のクレジットカードで立て替え、その後に他の参加者から現金を集めることで、カード会社のポイントやキャッシュバックを受け取ることができます。これは一見『ずるい』と感じられるかもしれませんが、実際はルール違反ではなく、むしろ賢い工夫の一例です。このように既存のルールを違反せずに新しい価値を見出すことが、ずるい考え方の本質です。
この手法は、一般的な支払い方法を少し変えただけで、大きなメリットを享受できることを示しています。また、この柔軟な発想は『ラテラルシンキング(水平思考)』とも呼ばれ、既存の枠にとらわれず自由な発想で問題解決に取り組む姿勢を推奨しています。ラテラルシンキングは、問題解決のための柔軟な手法を提供し、特に、新しいアイデアを求められるビジネスシーンで役立つ力です。常識にとらわれず、工夫を凝らしたアイデアは、チームやプロジェクトに大きなインパクトをもたらすことでしょう。
3. ラテラルシンキングの重要性
3. ラテラルシンキングとは、固定観念や既成概念から解放され、新しい視点を持つための思考方法です。この思考法は、何かを達成するために既存のルールに縛られず、様々な視点からアプローチすることを促します。具体的には、通常では見過ごしてしまうような解決策を見つける力を養うことができます。
ラテラルシンキングの実践例として、飲み会での支払いを自分のカードで立て替え、後にポイントを得る方法が挙げられます。これは既存のルールを遵守しつつも、その中で最大限の利益を引き出す工夫です。このようにラテラルシンキングは柔軟な考え方を可能にします。
ラテラルシンキングの重要性は、ロジカルシンキングと対比されて語られることが多いです。ロジカルシンキングは、問題を解決するための論理的な手順を重視しますが、ラテラルシンキングは直線的な道筋に囚われないことが特徴です。これにより、思いもしなかった新しい解決策や革新的な発想を生み出すことができます。例えば、1970年の大阪万博では入場者の動線改善にラテラルシンキングが活かされました。この工夫により、少ない手間で多くの効果を得ることが可能となりました。
ラテラルシンキングを身につけるためには、「疑う力」、「抽象化する力」、そして「セレンディピティ(思いがけない発見)」の3つの要素が必要です。疑う力は、常識の枠を外れ、新しいアイデアを生む原動力となります。抽象化する力では、問題の本質を見極め、様々な視点から解決策を見出すことを助けます。セレンディピティは、思わぬところでの発見を可能にし、新たなチャンスをつかむための感性を磨く力です。これらの力を活かして、常に柔軟な視点で物事を捉え、より豊かな発想力を養いましょう。これこそが、ラテラルシンキングの真の価値と言えるでしょう。
4. ラテラルシンキングの基盤
この記事では、『ずるい考え方』という一見ネガティブな響きを持つ言葉が、実際にはどのように発想力を養うかについて考察します。著者である木村直吉さんは、「ずるい」とは通常のルールを超えて新しい視点を持つことを意味し、そのためのトレーニング法を提案しています。ここでは特にラテラルシンキング、つまり水平思考の基盤について探ります。ラテラルシンキングの基盤となるのは、既存の枠を外れる勇気と目的を達成するためのクリエイティブな方法を模索する姿勢です。著者は、これを理解するための具体例として、1970年に開催された大阪万博での入場者動線改善を挙げています。当時、少ない手間で効率的に大量の人を捌くための仕組みが導入され、大成功を収めたケーススタディです。
この考え方を実践するためには、まず常識を疑う「疑う力」が必要です。日常の当たり前を見直すことで、新たな発見の扉が開かれます。また、本質を捉える「抽象化する力」も重要です。これは、新しいアイデアを得る際の指針となります。そして、偶然の出来事を活かす「セレンディピティ」、思いがけない発見を日常に取り入れるための準備が不可欠です。これらのスキルは単に読書で得られるものではなく、実際の生活で試行錯誤しながら身につけることが求められます。
本書は単なる発想法だけでなく、我々の生活や仕事に直接的に役立つ知恵を提供しています。新たな光を見つけたいと望む全ての人にとって、参考になる内容が満載の一冊です。是非手に取って、新しい世界を発見する契機にしてみてください。
5. 身に付けるべき3つの力
この本を通じて、私たちは新しい視点を得て、柔軟な発想を身につけることができます。
発想力を向上させるためには、「疑う力」「抽象化する力」「セレンディピティ」という3つの力が重要となります。
それぞれの力を身につけることで、発想力が格段に向上します。
それでは、一つずつ解説していきます。
私たちは日常生活の中で多くの常識に縛られがちです。
しかし、常識を一度疑うことで、新しい視点が生まれ、自分でも思いも寄らないアイデアを出すことができるようになります。
この疑う力を鍛えることで、既成概念の枠を超えることが可能になります。
具体的な情報や事実に囚われず、本質を理解することによって、私たちはより柔軟に考えることができるようになります。
これが発想力の強化に大いに役立つのです。
これは偶然を活かすための感性を研ぎ澄ます能力です。
日常の中で起こる思いがけない出来事を受け入れ、それをヒントに新しいアイデアを生み出す力とも言えます。
このセレンディピティを磨くことで、予測不能な状況にも対応でき、より創造的な発想をすることが可能になります。
この本を手に取り、自分自身の発想力をさらに高めてみてください。
6. 最後に
この本では、「ずるい」という言葉が持つ新たな意味を理解することを通じて、発想力を鍛える方法を学ぶことができます。
通常、ずるいと聞くとネガティブなイメージを持ちがちですが、この本ではそれを逆手に取り、既存のルールや常識に捕らわれない柔軟な思考について具体例を交えて解説しています。
これは一見ずるいと感じるかもしれませんが、ルール違反ではなく機知に富んだ発想の一つです。
著者は、こうした発想を『ラテラルシンキング(水平思考)』と呼び、ロジカルシンキング(論理的思考)と対比させています。
その象徴的な成功例の一つとして、1970年に行われた大阪万博での入場者の動線改善が挙げられます。
こうした取り組みは、少ない手間で想像以上の成果を生む可能性を秘めています。
疑う力は常識を疑って新しい視点を生み出すカギとなり、抽象化する力は物事の本質を捉えるための重要なスキルです。
そしてセレンディピティは、偶然に訪れるチャンスを掴むための感覚を磨く力とされています。
これが、あなたの生活や仕事に新たな視点と光をもたらしてくれることでしょう。
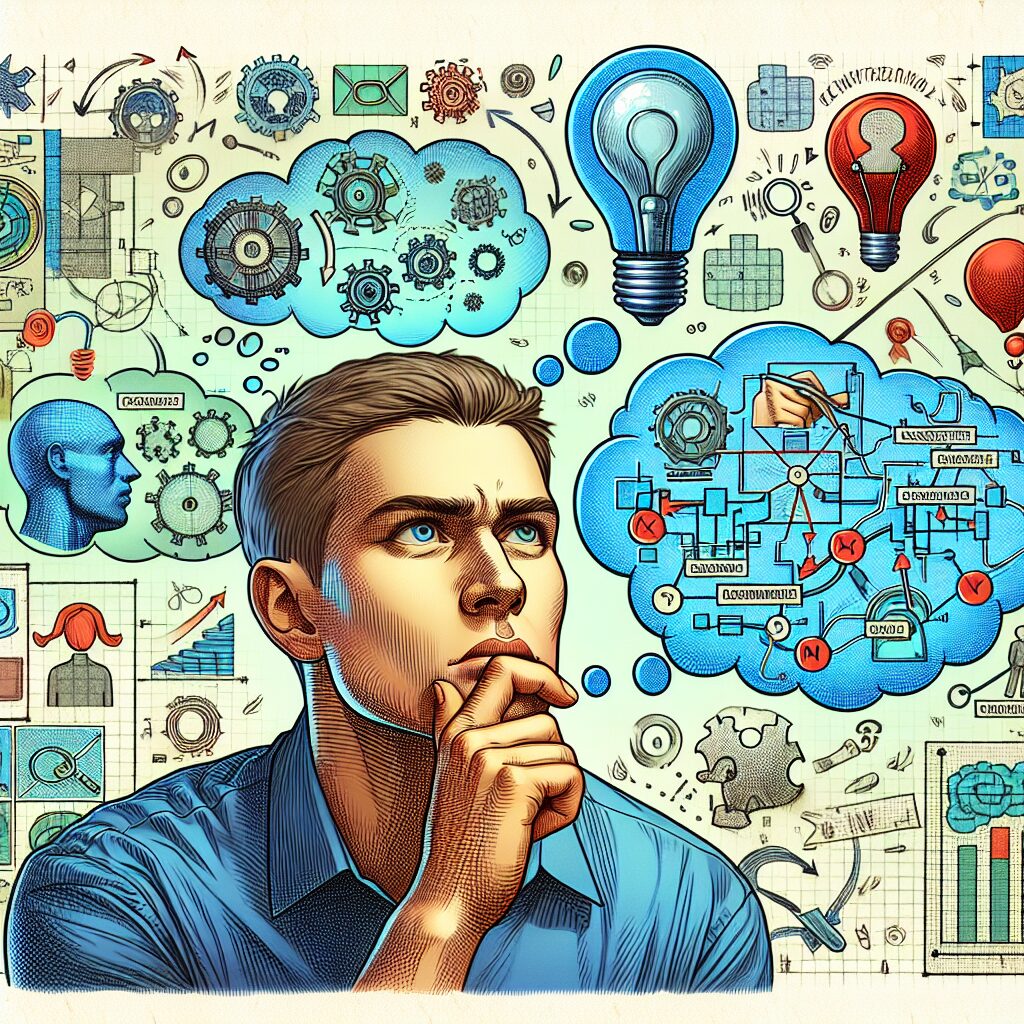


コメント